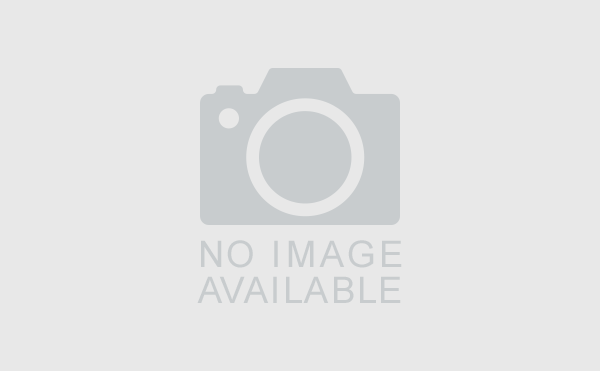人は本をつくってきたんだなあ。
ここ数年の朝ドラや大河ドラマでは、「本をつくる」ことに関する内容をよく目にします。
そのたびに、それぞれの登場人物の本づくりへの思いに胸を打たれ、
(たぶんだれも狙ってないところで)涙腺が緩んでしまいます。
朝ドラ「らんまん」では、植物学者である主人公が、
学会の冊子や植物図鑑をつくるために奮闘します。
時代は明治時代、印刷会社に弟子入りし、下絵を描き、紙に絵を刷るところまで
すべて学びます。自宅に印刷機を買い、自分で図鑑をつくっていきます。
まさに執念です。日本の植物を明らかにする。
間違いなく、日本の植物学の礎を気づいたうちのひとりだと感じます。
そこからうんと時代をさかのぼり、平安時代。
大河ドラマ「光る君へ」では、紫式部が書いた『源氏物語』を
一条天皇にプレゼントしようと、中宮彰子が製本する場面があります。
もちろん、下々の者と一緒に作業してつくり上げるのですが、
表紙の紙をどんな色のどんな和紙にしようかと考えたり、
ひもで本を束ねたりする作業を中宮自らしています。
一条天皇が源氏物語を好んでいるからこそ思いついた贈り物だとしても、
本を贈る、自分で製本する、という行為に愛情を感じ、感動してしまいました。
そして時代は江戸時代。
現在放送中の大河ドラマ「べらぼう」では、まさに本づくりの毎日です。
版元になるべく奮闘し、いろいろな人の知恵を借り、
絵師や作家との縁を結び、どうすれば売れる本をつくれるかと知恵を絞る……。
もし、蔦谷重三郎が現代に生きていたら、
いったいどんな新しいものを生み出してくれるのかとわくわくします。
本は人間にとってずっとなくてはならないものであり続けるだろうな、と感じます。
電子化されていく時代ですが、
それでも図書館があり、本屋にはたくさんの本が並んでいます。
まだまだ紙の良さは捨てられません。
でも時代とともに減っていくのは確かですから、
その流れにのりつつも、紙の出版物へのこだわりももっておきたいですね。
ヨーコ